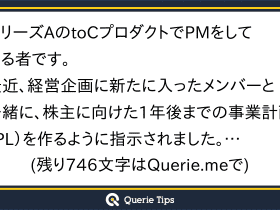
シリーズAのtoCプロダクトでPMをしている者です。最近、経営企画に新たに入ったメンバーと一緒に、株主に向けた1年後までの事業計画(PL)を作るように指示されました。この事業計画では、「いつ・どの数値を・どのくらい上げるか」を、過去の施策で得た学びをもとに描いてほしいと言われています。これまで数年サービスをやってきているなら数字を見通せない訳はない、シリーズA以降はこのやり方でやらないとダメと言われました。理想のPMは、一年後までどの数字をどの施策でどのくらい上げられるかを見通しているのでしょうか?根拠のない数字を掲げても、達成できてもできなくても誰も責任を取らないから、と、PMが計画と共に策定することが重視されています。この方針自体は一理あると思うし、計画づくりにPMが巻き込まれるのはありがたいことだと感じています。(上から謎の数字が降ってくるより、コミットしやすい計画になると思います。)が、これまでやったことがない動き方なので大変戸惑っています。今の私は「今後やる施策の結果を見て、次に何をやるか決める」ような探索的なサイクルでしかプロダクトを動かした経験がなく、「この数字を上げるためにこれをやる」と1年分のロードマップを先に描いたことがありません。自分たちのアウトプットがどのくらいの結果を出せるかの学習が少ないのが原因かなと思っているのですが、全然その辺の感覚がなく、できることはやって結果が上振れることも下振れることもあって、どうしたらいいのだろうと思っています。このような経験は、Akiさんにもあったでしょうか?・PMとして事業計画に対してどのようにコミットされたか・どのようにして「施策と数値の関係性」への理解を深めていったのか・事業計画を引くときに、どこまで仮説で描き、どこから柔軟性を持たせているのかなど、何かご経験や考えがあれば教えていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。 新たな発想を生み出す質問箱 Querie.me
DRANK
シリーズAのtoCプロダクトでPMをしている者です。最近、経営企画に新たに入ったメンバーと一緒に、株主に向けた1年後までの事業計画(PL)を作るように指示されました。この事業計画では、「いつ・どの数値を・どのくらい上げるか」を、過去の施策で得た学びをもとに描いてほしいと言われています。これまで数年サービスをやってきているなら数字を見通せない訳はない、シリーズA以降はこのやり方でやらないとダメと言われました。理想のPMは、一年後までどの数字をどの施策でどのくらい上げられるかを見通しているのでしょうか?根拠のない数字を掲げても、達成できてもできなくても誰も責任を取らないから、と、PMが計画と共に策定することが重視されています。この方針自体は一理あると思うし、計画づくりにPMが巻き込まれるのはありがたいことだと感じています。(上から謎の数字が降ってくるより、コミットしやすい計画になると思います。)が、これまでやったことがない動き方なので大変戸惑っています。今の私は「今後やる施策の結果を見て、次に何をやるか決める」ような探索的なサイクルでしかプロダクトを動かした経験がなく、「この数字を上げるためにこれをやる…